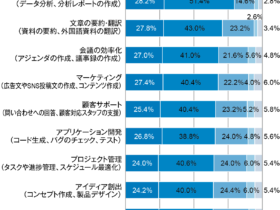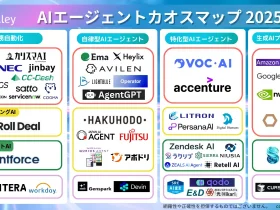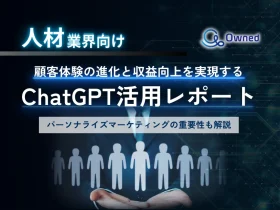国立科学博物館は6日、遠隔操作ロボットを使用した博物館鑑賞事業を実施すると発表した。

写真提供:牧野一浡
本事業第1弾として、近代植物分類学の礎を築いた牧野富太郎博士をテーマに博士の標本を数多く所蔵する同館と博士の終の棲家である牧野記念庭園(東京都練馬区)、博士の功績を広く伝える高知県立牧野植物園(高知県高知市)の3館・園をロボットで操作し、博士の業績を辿る。
本事業は地域の博物館等と連携し、どこにいても、全国各地の博物館(植物園)を巡り、鑑賞体験を提供する事業として、「令和3年度文化芸術振興費補助金地域と共働した博物館創造活動支援事業」の補助金を受けて実施するもので、ポストコロナを見据えた博物館鑑賞モデル事業として実施するもの。
開催概要
 開催日時:2021年12月9日(木)10:30から(約1時間)
開催日時:2021年12月9日(木)10:30から(約1時間)
内容:国立科学博物館、練馬区立牧野記念庭園、高知県立牧野植物園の3館・園を相互にロボットを遠隔操作・鑑賞。なお、参加者は各館・園にて募集済。
使用するロボット:アバター「new-me(ニューミー)」(avatarin提供)
牧野富太郎博士は、現在の高知県高岡郡佐川町に生まれた。高知の豊かな自然に育まれ、幼少から植物に興味を持ち、独学で植物の知識を身につけた。二度目の上京のとき、東京大学理学部植物学教室への出入りを許され、植物分類学の研究に打ち込むようになる。自ら創刊に携わった「植物学雑誌」に、新種ヤマトグサを発表し、日本人として国内で初めて新種に学名をつけた。94年の生涯において収集した標本は約40万枚といわれ、蔵書は約4万5千冊を数える。新種や新品種など約1500種類以上の植物を命名し、日本植物分類学の基礎を築いた一人として知られている。現在でも研究者や愛好家の必携の書である「牧野日本植物図鑑」を刊行。全国からの要望に応じて各地を巡り、植物を知ることの大切さを一般に広く伝え、植物知識の普及にも尽力した。1953年東京都名誉都民。1957年文化勲章受章。